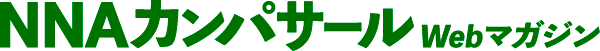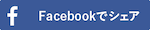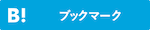【プロの眼】戦場のプロ 傭兵・高部正樹
第1回 「100万人に1人」の男
アジアの戦場を目指す
初めまして。高部正樹と申します。1980年代からアフガニスタン、ミャンマー、ボスニアなどで傭兵や義勇兵として戦いました。現在は軍事評論家として執筆、講演などをしており、この連載ではアジアの戦場を中心に私の経験をお伝えします。傭兵とはいえ四六時中、戦闘ばかりしているわけではありません。給料や食事、国際色豊かな仲間たちや現地の人々の文化・国民性まで、「戦場の現実」を幅広く紹介していきます。

アフガニスタンの拠点ジャジで銃を手にする筆者(左奥)。仲間のイスラム戦士「ムジャヒディン」たちと(筆者提供)
きっかけは、小学生の頃に親が買ってくれた1冊の本です。太平洋戦争を題材とした子供向けの戦記物で、必死に戦う日本兵たちが描かれていました。その姿に心を奪われ、戦記物を読みあさるうちに「軍人は自分以外の誰かのため、何かのために命を懸けて戦う。これこそ男の仕事だ」と確信。将来は軍人になろうと心に決めました。
「どうせなら、最前線で戦う戦闘機のパイロットか歩兵を目指そう」と思いました。『大空のサムライ』著者の坂井三郎氏を深く尊敬していた私は、高校3年生の時に航空自衛隊のパイロットになるべく「航空学生」(※)を受験します。もちろん大学を卒業してから目指すコースもありましたが、一日も早く憧れた戦闘機乗りになるために迷うことなく航空学生を受験。運よく高倍率を突破し、入隊しました。
※自衛隊が高校卒業生から航空機の操縦者要員を採用・養成するコース。高部氏によると「3000人弱の受験生に対して合格は100人ほど」といい、30倍近くもの高倍率だったという
「航空自衛隊随一のエリート集団」(隊司令)とおだてられ、航空学生の2年間は厳しい体育訓練と座学の毎日でした。航空機力学、電子工学など専門分野に加えて戦史や変わったものでは社交ダンスもありました。それらは幹部自衛官になるための教育だったようです。
駆け足は毎日どれくらい走らされたか記憶にありません。病気やけがも「走れば治る」と言われるほど鍛えられました。1日10キロメートルならラッキー。時には10キロと言われて帰ってくると「はい、アップおしまい。今から10キロ計測。40分切れなかったらもう1本」。何とか時間内に戻ると「よし。じゃ(クール)ダウン10キロな」という具合です。
訓練以外にも強制加入のクラブ活動で走り、深夜や明け方の非常呼集で叩き起こされて走り、1日のほとんどを走っていた気がします。厳しく辛い毎日でしたが、精神的にも肉体的にも後の傭兵生活の基礎となったように思います。
挫折したパイロット
最前線の歩兵に転身
2年間の課程が終わると飛行幹部候補生に任官し、いよいよ飛行訓練。しかし、私は訓練で体にかかるG(加速度)の負荷により腰を痛め(第三腰椎分離症と診断)、パイロットの道を閉ざされました。「もう戦闘機に乗れない」と一時やけ酒におぼれます。
ところがある日、ふとわれに返ります。「あれ、そもそも戦闘機乗りになりたかったんだっけ。いや、俺がなりたいのは最前線に立つ軍人だよね」と。私はもう1つの目標だった歩兵になろうと決意します。でも当時、自衛隊は戦うどころか海外派遣も考えられない時代。 日本にこだわる必要もないと思い、海外の戦場を目指すことにしました。
インターネットもない当時、手掛かりはない上に「傭兵なんて小説や漫画の話だよ。実際にある訳ない」「日本で普通の仕事につくべき」と周囲から言われました。
それでも一筋の望みを懸け、アフガニスタンで取材経験があるジャーナリストに手紙を書いて、力になって欲しいと頼みました。すると、現地に精通した強力なコネがあるという人を教えてもらえました。ただ、訪ねはしたもののほぼ門前払いされます。
私は、その頃に得られた手掛かりとして「パキスタンのペシャワルという町、ユニバーシティ通りという所にソ連を相手に戦うムジャヒディン(イスラム側の戦闘員)のオフィスがあるらしい」という微かな情報だけを頼りに、パキスタンに飛ぶことを決意しました。
今思えば、旧ソ連やアフガン政府のスパイがはびこるペシャワルで「ムジャヒディンのオフィスはどこですか?」などと聞いて回るのは自殺行為ですが、当時の私はそこまで頭が回らないほど未熟かつ必死でした。
そしていよいよ成田を飛び立つ前日、礼儀としてあいさつはしなければと思い、事情通の人を再び訪ねます。すると驚いた様子で私を迎え入れ、もう一度話を聞いてくれました。
「男が1,000人いたら君のように戦いたいと考えるのが1人くらいはいる。でも実際にやる人間は100万人に1人だ。君も1,000人の1人と思っていたが、もしかしたら100万人に1人だったのかもしれないな」
そう言うと目の前で紹介状を書き、「着いたらここに連絡しなさい。私の紹介と言えば悪いようにはしないだろう。健闘を祈る」と電話番号のメモも一緒に渡してくれました。翌日、私はそれを持って飛行機に乗り込み、一路イスラマバードを目指しました。
パキスタンの洗礼
「インシャラー」

パキスタン北西部の都市ペシャワル(筆者提供)
これが人生初の海外渡航でしたが、目指す先は戦場。水筒やナイフはもちろん、衛生環境が最悪と聞いていたので下痢止めや抗生物質なども用意し、他はわずかな着替えだけスーツケースに詰め込みました。スーツケースを使うのは、目立たない旅行者を装うためです。
海外の一人旅は、最初から強烈な洗礼でした。田舎の倉庫みたいに粗末なイスラマバード空港では税関で当たり前のように賄賂を要求され、あまりのしつこさにしぶしぶ乗ってしまったタクシーは、大して良くもないのに1泊100米ドル近くもするホテルに連れて行かれた上、高額なチップまで請求される始末です。
それでも翌日、パキスタン北西部の主要都市ペシャワルに無事到着。異国情緒の漂うにぎやかな街です。1泊200円程度の安宿に部屋を確保し、すぐにメモの番号に電話します。紹介状があると告げると翌日、ひげ面のいかつい男がホテルに現れました。しかし、時計を見れば既に昼12時過ぎ。前日は電話で9時にと言っていたので、そのことを尋ねると「インシャラー」という言葉が返ってきました。
「インシャラー」。その後、散々悩まされることになる言葉です。「神の思し召しのままに」という意味らしく、つまり何が起きても「全ては神様が決めたこと」になるのです。時間に遅れても「インシャラー」、戦友が亡くなっても「インシャラー」。最初はさすがに辟易(へきえき)しましたが、慣れるにつれ自分も使うようになったから不思議なものです。
「私は医者です」
どうにかごまかせ

さらに翌日にはアフガニスタンまで共に行くムジャヒディン数人と合流。リーダーが私に「今から国境を越えるまで、お前は一切声を出すな。この先は外国人立ち入り禁止区域。途中の検問でばれたら拘束される」と警告します。私の荷物に触れながら「固い物は着替えでくるんで荷物の中央に。触って固い物があると開けろと言われる」「検問では警官と決して目を合わせるな」などの注意も与えられました。
そして最後に「マン・アズ・ドクトル。ミリ・パラチナール(私は医者でパラチナールに行く)」という言葉を教わりました。どこの言葉か分かりませんが、「お前はハザーラ族やトルクマニーに見えるから、どうしようもなくなったらこれでごまかせ」と。発音でばれるだろうと聞くと「パキスタン人だってその言葉のネイティブではない。この辺りは民族のるつぼだ」と言って高笑いしていました。これも「インシャラー」なのでしょう。
その後、車がごった返すバス乗り場でマイクロバスに乗車。戦場に向かうのに乗り合いバスとは意外かもしれませんが、この方が目立たないのです。本や映画とは違い、現実では「いかにも」ということはしません。大事なのは「静かに人の波に紛れる」ことです。
ペシャワルから一路南下して密造銃で有名なダラを通り過ぎ、目指す先は国境の町パラチナール。平原と岩山が続く単調な風景の中、バスは猛スピードで突き進みます。途中にあった十数カ所の検問は助言通りにやり過ごし、約8時間後パラチナールに到着しました。
「もう、大丈夫だ」
念願のアフガン入り

パキスタン国境の町パラチナール(筆者提供)
パラチナールは、賑わっていたペシャワルとは全く異質な町です。陰鬱(いんうつ)な空気に満ち、目つきが鋭い山賊のような男たちが銃を手に闊歩(かっぽ)していました。だらしなく寝そべる老人は銃声がしてもぴくりとも動きません。緊張と怠惰、相反する空気で混沌とした雰囲気に慣れることができませんでした。
車を乗り換え、さらに先のテラマンガルに向かいます。掘っ立て小屋のような店が何軒か並ぶだけの集落ですが、カセットデッキから民族音楽が大音量で流れる中、まだ戦地の空気をまとった者やこれから戦場に向かう者など、ムジャヒディンで溢れ返っていました。
完全武装したパキスタン陸軍の兵士もいますが、ここでは肩身が狭そうに歩くしかありません。絵に描いたようなアウトローの世界です。そこかしこで銃声が響き、ちょっとしたいざこざでもすぐに命の奪い合いに発展するであろうことは想像に難くありません。
迫力を漂わせる男たちのすぐ向こうに、巨大な絶壁がそびえています。頂上へ向かって未舗装の粗末な一本道があり、中腹の大きな要塞にはパキスタン国旗が翻ります。その崖の上が、目指すアフガニスタンだと教えてもらいました。
ピックアップトラックの荷台に乗り込み、その道をゆっくり登るうちにテラマンガルの集落がはるか下になりました。頂上の手前はパキスタン陸軍の最後の検問ですが、もうチェックはありません。ゲートは開放されていて、止まることなく通過すると木製の粗末な門があります。そこを潜り抜けた瞬間です。
「アフガニスタ――ン」
男たちが大声を出して手を叩き、これまで厳しかった顔が一気に緩みました。「アフガニスタンにようこそ。もう、大丈夫だ」みんなが声を掛けてくれます。戦争のない国から戦場入りしたのに「もう大丈夫」とは少し変な気分ですが、やっと念願のアフガニスタンに到着です。仲間と肩を組んで喜びました。
傭兵になる。そう決めてから長い道のりでしたが、ようやく一歩を踏み出した瞬間でした。
バクシーシの猛攻
携行品を死守せよ

アフガンの質素な小屋「マルカズ」(筆者提供)
近くのジャジという拠点に入る頃にはすっかり暗くなりました。泥を固めて作ったマルカズと呼ばれる質素な小屋が3棟ほどあるだけの小さな拠点ですが、翌朝になって周囲の風景に圧倒されました。
高台にあるジャジは雄大な景色に囲まれていました。時計に付いていた高度計を見ると2,700メートル。東は遠くまで平原が続き、アフガニスタン奥地に続く西の大地は乾いた砂と岩の丘陵地帯。その西の端から険しい岩だらけの山脈が北方へと続いています。
風光明媚(めいび)で少しのどかな気分でしたが、すぐに吹き飛ばされます。マルカズの横に回ると、KPV重機関銃が空をにらんでいました。ソ連製14.5ミリの重機関銃です。ここは戦場だったな、と現実に引き戻されるしかありませんでした。
そしてさらに奥地を目指しますが、ここでアフガニスタンの洗礼を受けることになります。
ジャジに置いていく荷物を整理していると、長老らしき人が近付いてきます。私がペシャワルで購入した毛皮の帽子を手に取ると「バクシーシ?」と一言。私が思わず「イエス」と答えると、長老は大喜びで帽子を被って行ってしまったのです。その瞬間、言葉の意味に気付きましたが、後の祭りでした。
「バクシーシ」とは要するに「施し」です。現地では富める者が貧しい人に施しを与えるのは当然、という慣習があります。実際、お金はあまり無いのですが、日本から来た私は彼らには富める者に見えるのでしょう。ボールペンのようなちょっとした物を貸しても「バクシーシ」と言いながら持ち去り、決して返してくれません。必要な物は困るので「パキスタンに帰る時にあげるから今は勘弁して」と言う他にありませんでした。
その後、所属した最前線部隊のコマンダー(司令官)が海外留学の経験があるインテリだったことが幸いし、注意をしてくれたおかげでバクシーシ攻撃は下火になります。でも結局、パキスタンに戻る時は毎度、所持品がほぼ無くなる有りさまでしたが…。
(次号、初陣参加の話に続く)

ジャジに配置した対空用の重機関銃(筆者提供)