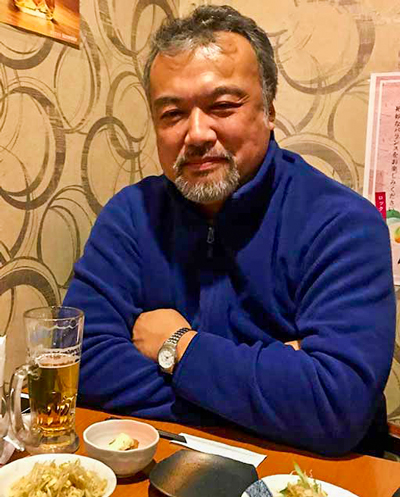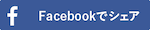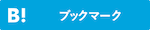【プロの眼】インド食文化のプロ 小林真樹
最終回 食の習慣は食材で変わる
インド食文化の原点回帰
さまざまな食習慣や食の戒律を持つ外国人が日本という異国の地に来て、真っ先に直面するのがそれまで当たり前に摂取してきた食材の確保です。彼らは日本で食材をどのようにまかなってきたのか。習慣や戒律の問題をどう解決し、どう妥協してきたのか。最終回は、食材を通じて垣間見える日本の南アジア系コミュニティーの動向をご紹介したいと思います。
 東京都江戸川区のインド食材スーパー「アンビカベジ&ヴィーガンショップ西葛西」では、インド直輸入の生鮮野菜も販売している(筆者提供、以下全て同)
東京都江戸川区のインド食材スーパー「アンビカベジ&ヴィーガンショップ西葛西」では、インド直輸入の生鮮野菜も販売している(筆者提供、以下全て同)
日々の食事は単に生命を維持する上で欠かせないだけではなく、その人が背負ってきた文化や歴史を色濃く反映します。多様な自然環境と宗教が混在するインド亜大陸では、食の領域でも地域・宗教の差が極めて大きく、改めてその広大さや重層性を感じさせます。
最近、ハラルという言葉を耳にする機会が増えました。イスラム法で「合法の」「許されている」を意味します。対義語にハラムという言葉があり、「非合法の」「許されていない」という意味になります。全てのイスラム教徒は、このハラルかハラムかという規範にのっとって生活、行動しています。
さて、日本のようなイスラム教の影響が希薄な国に、イスラム教徒が来た時に直面するのがこのハラル・ハラム問題です。
イスラム教が飲酒や豚肉食を禁じていることは広く知られています。しかし、たとえ牛や羊といった肉でもイスラム法に基づいた方法で屠畜(とちく)する必要があります。このようにイスラム法に基づいて適切に処理され「許可された」食材は、ハラル食材と呼ばれます。

豊富なハラル食材が並ぶ食材店

ハラル認証マークの付いた冷凍肉
識別が難しい加工食品は、豚やアルコールといったハラム成分が入っていないことを示すハラルマークの表示によって、イスラム教徒が安心して食べることができるのです。
1980年代に来日し、当時食事に苦労していたパキスタン人らによって細々と始められた国内ハラル・ビジネスは、訪日イスラム教徒の増加とともに注目され多くの業者が参入。新たな巨大マーケットとして熱い視線を集めています。調達や販売環境も整備され、今ではインターネットなどでも気軽にハラル食材が手に入るようになりました。

日本で再現されたネパールの伝統行事での食事風景
こうした中、ハラルに関する認証を拡大解釈する動きが進んでいます。元来、単にハラム成分が入っていないことを示すはずだったハラル表示が、ペットボトルの水や野菜といった本来はハラルかハラムかを問われない食材にまで付けられるなど、彼らの食生活を律する新たな動きが見られるようになったのです。
もちろん、多くのハラル食材が市場に出回ることで選択の幅が広がり、イスラム教徒にとってより宗教的に純化した食生活も可能となったこと自体は歓迎すべきことなのかもしれません。
しかし、例えばムガル時代の宮廷ではワインが盛んに飲まれていたように、本来もっと柔軟であったはずの食の戒律が異国の地で先鋭化することで、イスラム教徒の社会的な孤立や保守化を懸念する声が一部にはあることも事実です。
本国ではNGの牛肉食
焼肉楽しむネパール人

インド食材スーパー「アンビカ」の店内
一方、イスラム教徒とは対極の食事観を見せるのがネパール人です。もちろん、ネパールにも厳格な宗教的戒律は存在しますが、特に若い世代の間で急速に伝統離れが進んでいます。ネパールは他国での労働を政府が後押ししている国ですが、国外に出ることでこの意識は加速するようです。
例えば、日本で働くネパール人の中には、本国ではタブーとされている牛肉食すら享受し、休日に家族や友人たちと焼き肉店で卓上コンロを囲むような人たちが少なくありません。
しかし、その一方で日常的には故郷と同じか、あるいは故郷では廃れてしまった料理や祭礼の食習慣が見直されるケースもあります。異国にいるからこそ故郷を客観視でき、価値のあると感じたものを再現、再生産する。かつて、古老から受け継がれてきた手順や方法も、今やネットで容易にアクセスできます。
つまり、伝統離れとはいっても完全に喪失した訳ではなく、時に母国では体験できない異国ならではの食事を楽しみながら、時には母国以上に伝統的な食事を再現している姿が見られるのです。これも、日本で働くことで手にした可処分所得によって可能となった食の選択肢の広がり、と見ることができます。
外国産はふさわしくない
ヒンズーの大地母神信仰
パキスタンとネパールに挟まれたインドはどうでしょう。ヒンズー教徒もまた食に対して非常に保守的な人たちです。
特に宗教的な浄・不浄の意識が強く、身元の分からない人が作る外食を避け、可能な限り母や妻といった身内に作ってもらう傾向が今でも根強くあります。とりわけ菜食主義者が多く、時には肉料理を食べる人たちとの同席すら拒みます。
この菜食主義、実は単に野菜であれば何でもいいという訳ではないのです。
ヒンズー教の原理の一つに大地母神崇拝があります。ヒンズー教の人々が人生を送る「バーラト」と呼ばれる領域こそが神聖な、母なる大地であるとする思想です。戦前の日本を神州とする見方と似ているかもしれません。ちなみに、このバーラトとは現在のインド憲法に記載された正式な国号でもあります。
この思想に基づくと、聖なるバーラトの大地で産した野菜こそが浄なる食べ物であり、外国産の野菜はヒンズー教徒にとって本来ふさわしくないものと見なされます。
もちろん、この考えは極端に原理的で一般のインド人で実践する人は皆無です。日本在住のインド人たちも、近所のスーパーで購入した国産や輸入野菜を用いて日々の料理を作っています。
日本の野菜は甘過ぎる
インド野菜の輸入加速
一方、こうした宗教的規範とは別に、純粋な味の違いから日本の野菜に不満を感じるインド人が少なからずいます。
例えば、同じニンジンでもインド産と日本産とでは形も味も違います。日本の野菜は糖度が重視されるせいか、インド人にとっては甘過ぎると感じるらしいのです。
こうした需要に応えるため、近ごろはインドから生鮮野菜を輸入販売する動きが加速しています。日持ちする乾燥穀物や香辛料が主体だったインド系食材店の棚に、色とりどりの生鮮野菜類が陳列されるようになったのです。
折しも空前のヨガブームに後押しされ、菜食料理にスポットが当たることも多くなった昨今。日本の甘い野菜と本国インドから直輸入した野菜の味わいの違いをきっかけに、改めて母なる大地バーラトの神話に思いを寄せ、自らのルーツやアイデンティティーに目覚めるインド人もいるかもしれません。
これもまた食材の多様化によってもたらされた、食を取り巻く考え方や生き方の変容と見ることができるでしょう。
流通網の発達による選択肢の拡充と高度な情報化で、現在日本に住む南アジア系コミュニティーの食事情はかつてないほどあらゆる方向に進化、あるいは深化しています。
今後、このダイナミックな動きがどのように変貌を遂げていくのか。あるいはその先、コロナを克服した彼らが新しい世界でどのような食文化を形作っていくのか、いつか再び報告できる日を楽しみにしています。全6回にわたる連載を読んでいただいた皆さま、ありがとうございました。