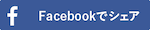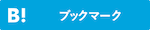「東西」の本から「亜州」を読み解く
アジアの本棚
『病が語る日本史』
酒井シヅ 著

新型肺炎の世界的流行で、文豪カミュの小説『ペスト』を始め、人類と病気をテーマにした本が改めて読み直されているようだ。本書は、高名な医学史家による日本人と病(やまい)の関係を概観したもの。初版は10年以上前だが、最近もメディアで引用されている。
藤原道長は糖尿病の重症化で死亡、鑑真和上は老人性白内障で失明、徳川家康は恐らく胃がんだった――など、文献に残された症状から歴史上の人物の病名を推理するあたりはリモート診断のようで興味深いが、今の状況下ではやはり日本人が感染症とどう戦ってきたかに注目したい。
島国の日本では感染症の多くは海外から流入して来た。筆者は8世紀ごろの天然痘流行は、中国大陸から入って来たと推理している。平安末期の久安6年(西暦1150年)にインフルエンザが流行したが、この時は宋の商人が持ち込んだという。
江戸時代の鎖国は感染症の予防には有効だったようだが、それでも18世紀には欧州で流行したインフルエンザが唯一の貿易港、長崎から国内に流入した。江戸末期の安政5年(1858年)には、米国船の乗組員が持ち込んだコレラが全国で猛威を振るった。
幕府が招いたオランダの軍医が防疫に活躍し、西洋医学の効果が認識されるようになったが、外国人が感染源だったことから攘夷運動を刺激する結果にもなった。明治中期には日清戦争で出征した兵士の多くが、中国で眼病のトラコーマに感染。復員兵から全国の学童へと拡大している。
日本政府は、明治30年(1897年)にコレラ、ペスト、腸チフスなどを対象に伝染病予防法を制定したが、明治時代の日本はペストの流行に何回も苦しんだ。インドから輸入した綿花に混じって来たネズミが発生源と分かってきたが、綿花の輸入がストップすれば重要産業だった紡績工業は大打撃を受ける。
個別企業もネズミを防ぐ設備の導入などの対応を迫られ、当時も防疫と経済の両立が大きな課題となった。こうした経験を経て、日本社会は水際対策や初期防疫の重要性を認識、明治40年(1907年)をピークにペストの流行はなくなった。
本書を通じて、日本が天然痘や結核など多くの病気を克服してきたことがよく理解できるが、人類は常に新たな感染症と戦わねばならない。新型コロナウイルス感染症への対策では、過去の経験はどこまで生かされたのだろうか?
『病が語る日本史』
- 酒井シヅ 著 講談社学術文庫
- 2008年発行 1,050円+税