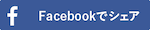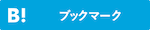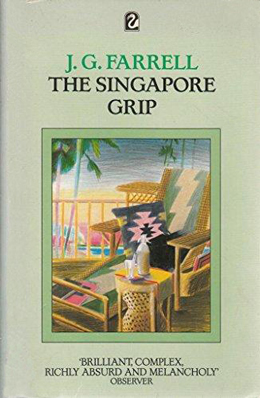「東西」の本から「亜州」を読み解く
アジアの本棚
『シンガポール・グリップ』
大英帝国最期の日々の記憶
1942年2月の日本軍によるシンガポール占領は、落日を迎えつつあった大英帝国に決定的な打撃を与えた。日本は以後敗戦までの3年半、シンガポールを昭南島と名付けて統治したわけだが、日本でこの時期のシンガポールを舞台にした小説は、佐々木譲の『昭南島に蘭ありや』(95年)くらいではないか。敗者となった英国人の方がシンガポール陥落についての小説やドキュメントを多く残しており、彼らにとってそれほど痛切な忘れがたい出来事だったことを示している。
『ナヴァロンの要塞』『女王陛下のユリシーズ号』で知られるアリステア・マクリーン(1922~87)も、デビュー間もない58年に『シンガポール脱出』(原題:South by Java Head)を書いている。マクリーンは戦時中、英海軍で巡洋艦に乗っており、45年には終戦に伴うシンガポール「解放」作戦にも参加した(一部ネット上には日本軍に捕虜になったことがある、との説が流布しているが、それは本人が酔っぱらって話したほら話だったらしい)。
陥落前夜、最後の船でシンガポールを離れたのは、謎めいた英軍将校、負傷兵や看護婦たちだったが、次々と危機が一行を襲う。インドネシアに漂着するも日本軍の捕虜となり…という冒険活劇だが、日本人は一貫して残虐な悪役。翻訳版が早川書房から出てはいるが、日本ではマクリーンの他の作品ほど親しまれなかったのも仕方がない。
今回推しておきたいのは、マクリーンより若い世代のJ.G.ファレル(1935~79)が78年に発表した『シンガポール・グリップ』(The Singapore Grip)だ。41年、ゴム園経営で財を成したシンガポールの財閥経営者、ブラケットは、次々に交際相手を替える奔放な長女の結婚に頭を悩ましている。そんなある日、亡くなった経営パートナーの息子、マシューがシンガポールにやって来た。娘の相手にぴったりだと考えたものの、当人たちに関心はなく、理想主義者のマシューは大陸から逃れて来た中国系女性と交際を深める。しかし、マレー半島に侵攻した日本軍はシンガポールに迫り、社会は混乱に陥ってゆく。
富裕な商人、植民地官僚、米国の軍人、華人と、主人公を取り巻く人物たちの群像劇の形で、アジアにおける大英帝国最期の日々を鮮やかに描いており、翻訳が出ていないのが不思議なくらいだ。題名は、人をとらえて離さないシンガポールの魅力を表しているが、もとはセクシャルな意味もあったようだ。
ファレルは、20世紀初頭のアイルランドを描いた『トラブル』(70)と、19世紀半ばのインドでの対英反乱(セポイの乱)を題材にした『クリシュナプール籠城戦』(73、ブッカー賞受賞)に続いて『シンガポール・グリップ』を書き、「大英帝国三部作」と呼ばれている。残念なことに、この小説家は本作出版の翌年にアイルランドで海に転落して亡くなった。まだ44歳で、本来ならその後も数々の大作を残しえたと思われる。生前「自分の人生で起きた最も興味深い出来事は大英帝国の没落だった」と話している。
『シンガポール・グリップ』は、戦争当時まだ幼かったブラケット一族の末娘ケイトがマシューの友人の1人と結婚し、76年の英国で平和に暮らしているところで終わるが、彼女にとって「シンガポールはもはや現実のものではない、子供時代の魔法の国のように思えた」。
私が初めてシンガポールに行ったのは81年。高層ビルも多くはなく、まだ英領当時の雰囲気も残っていたが、現在のマリーナ・ベイ周辺などを歩くと別の国のように感じる。香港も同様だが、英領だったことすら人々の記憶から次第に消えてゆくだろうという気もする。
『シンガポール・グリップ』
- J.G.ファレル 1978年発行
【本の選者】岩瀬 彰
NNA代表取締役社長。1955年東京生まれ。慶應義塾大学文学部を卒業後、共同通信社に入社。香港支局、中国総局、アジア室編集長などを経て2015年より現職